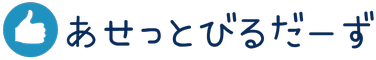「もしも」の時のために、生命保険は必要。そう漠然と考えていませんか?
実は、当社に寄せられるマネー相談の中でも、生命保険に関する相談はトップクラスの件数になっています。「なんとなく必要だと思って加入したのはいいものの、本当に必要なのかな?」と疑問を持つ方は少なくないと感じています。
実はファイナンシャルプランナーの中には、「生命保険は基本的に必要ない」と考える人もいます。
この記事では、なぜ「生命保険は必要ない」と考えるのか、その理由を5つのポイントに分けて解説します。
1. 日本の公的保障は非常に手厚い!
多くの人が民間の生命保険で備えようとするリスクは、実は国がすでに保障してくれています。
- 遺族年金: 働き手が亡くなった場合、子どもがいる家庭には国から遺族年金が支給されます。
- 高度障害年金: 障害を負った場合も、障害年金が生活を支えます。
- 高額療養費制度: 病気やケガで医療費が高額になっても、自己負担額には上限が設けられています。
これらの公的保障制度を詳しく知れば、民間の保険で備えるべきリスクは意外と少ないことに気づくでしょう。
2. 「貯蓄」と「保障」は分けるべき
終身保険や養老保険、学資保険といった貯蓄型の生命保険は、保障と貯蓄が一体になっています。「掛け捨てはもったいない」と考えて加入するケースも多いですが、貯蓄型の生命保険は、一般的に手数料(コスト)が高いというデメリットがあります。
保険で貯蓄を行うよりも、支払う保険料を掛け捨ての安い保険に充て、余ったお金を自分で投資信託や預金に回す方が、資産を効率よく増やすことも期待できます。
「掛け捨てはもったいない」と考える前に、まずは貯蓄と保障を分離して考えることが大切です。
3. 保険料は「安心を買うためのコスト」と考える
生命保険の保険料は、万が一の事態が起こらない限り、戻ってくることはありません。つまり、保険料は「安心を買うためのコスト」です。
人生の中で数百万〜数千万円にもなる保険料が、そのコストに見合うだけの「安心」をもたらしているのか、冷静に考える必要があります。
もし「保障よりも安心感が欲しい」という場合は、保障額は小さいものの、コストパフォーマンスに優れた『県民共済』などを活用するという手もあります。
4. 住宅ローンに「団体信用生命保険」が付いている
多くの人が生命保険を検討する理由の一つに、住宅ローンがあります。しかし、ほとんどの住宅ローンには「団体信用生命保険(団信)」が付いています。
これは、契約者が死亡または高度障害になった場合、残りの住宅ローンが完済されるという保障です。
手取り収入の20〜25%を占めることもある住居費が不要になるだけで、遺族の生活に必要な資金はかなり抑えられます。住宅という大きな資産が守られるため、他に高額な死亡保障を準備する必要性は低くなります。
5. 独身や子どもがいない夫婦には、そもそも大きな保障が不要
独身の方や、子どもがいない共働き夫婦の場合、万が一のことがあっても、経済的に困る人がいないケースが多いです。
かつては「社会人になったら、生命保険ぐらいは入っておかないと」と言われることもありましたが、今の時代は、お金を有限な資源として捉え、使わないお金は投資に回すなど、有効に利用する方が賢明だと考えられるようになっています。
少なくともこの場合には、葬儀費用や入院費用に備える最低限の保障があれば十分であり、高額な死亡保障は必要ないといえるでしょう。
ただし、生命保険が必要な人もいる
ここまで「必要ない理由」を挙げてきましたが、もちろん生命保険が本当に必要なケースも存在します。
- 公的な保障だけでは不十分な場合: 大黒柱に万が一のことがあった場合、遺族年金などの公的保障だけでは足りず、子どもの教育費や生活費を別で確保しなければならないケースです。
- 住宅ローンを組んでいない、または団信では不十分と考える場合: 団信のない住宅ローンや、借入額が少ない場合など、必要な保障を別途検討する必要があります。
まとめ:生命保険は「なんとなく」ではなく、「本当に必要か」を判断しよう
生命保険は「全員が必須」ではありません。実際、すでに十分な資産を形成している、いわゆる「お金持ち」と言われる人たちは、生命保険を必要としないともいわれています。
「保険に入る前に、まず自分のライフスタイルや公的保障の内容、貯蓄額を確認する」というステップを踏むことで、本当に必要な保障を見極め、無駄なコストを削減することができます。
その無駄をそぎ落とすことで、目的の資産形成が達成できるスピードも上がり、資産形成が進めば進むほど、生命保険はより必要のないものとなっていくでしょう。
あなたは生命保険に「なんとなく」加入していませんか?まずは一度、ご自身の状況を見つめ直すことから始めてみましょう