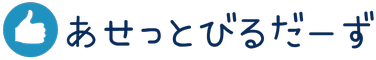「ふるさと納税って名前は聞くけど、なんだか難しそう…」
「やるとお得って聞くけど、どうやればいいの?」
そう思って、ふるさと納税をまだ始めていない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ふるさと納税の仕組みや具体的なやり方、そして「これだけは知っておきたい」控除限度額の計算方法まで、初心者の方でもわかるように丁寧に解説します。
この記事を読めば、あなたも今日からふるさと納税を始められます。ぜひ最後までご覧ください。
1. ふるさと納税とは? 2つのメリットを解説
ふるさと納税とは、「自分の好きな自治体を選んで寄附ができる制度」のことです。
寄附をすると、「税金の控除」が受けられ、さらに寄附した自治体から「返礼品」がもらえるという、まさに「一石二鳥」の仕組みです。
具体的に、以下の2つのメリットがあります。
メリット①:豪華な返礼品がもらえる!
お肉、お米、魚介類、フルーツ、家電製品、旅行券など、全国各地の特産品や名産品の中から好きなものを選んで受け取ることができます。
寄附額の3割程度が返礼品の目安とされているため、実質2,000円の自己負担で、数千円~数万円相当の豪華な返礼品を手に入れられるのが最大の魅力です。
メリット②:税金が安くなる!
寄附した金額のうち、自己負担額の2,000円を除いた全額が、所得税や住民税から控除されます。
たとえば、30,000円を寄附した場合、自己負担額の2,000円を除いた28,000円が税金から控除されることになります。
つまり、自己負担2,000円だけで、豪華な返礼品が得られるというわけです。
2. ふるさと納税の流れはたった3ステップ!
ふるさと納税は、以下の3ステップで完了します。
- 寄附する自治体と返礼品を選ぶ:インターネットのふるさと納税サイト(さとふる、ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税など)から、寄附したい自治体と返礼品を選びます。
- 寄附金を支払う:クレジットカードや銀行振込などで寄附金を支払います。
- 税金の控除手続きを行う:「ワンストップ特例制度」または「確定申告」のどちらかで税金の控除手続きをします。
「確定申告」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、後ほど解説する「ワンストップ特例制度」を使えば、確定申告は不要です。
3. 【これが一番重要!】ふるさと納税の限度額を計算しよう
「お得」と言われるふるさと納税ですが、無制限に寄附できるわけではありません。
寄附金額には上限があり、これを「控除限度額」と呼びます。この限度額を超えて寄附すると、自己負担額が2,000円以上になってしまいます。
控除限度額は、年収や家族構成によって異なります。
ご自身の限度額を知ることが、ふるさと納税を成功させるための最初のステップです。
簡単シミュレーションであなたの限度額をチェック!
多くのふるさと納税サイトには、簡単な質問に答えるだけで限度額を計算できる「シミュレーションツール」があります。
- さとふる:控除上限額シミュレーション
- ふるさとチョイス:控除額シミュレーション
ぜひ、ご自身の年収や家族構成を入力して、まずはざっくりとした限度額を調べてみましょう。
【FPが教える】自分で計算する方法
より正確な限度額を知りたい方は、ご自身の源泉徴収票を確認して計算する方法もあります。
計算式は複雑ですが、大まかな目安は以下の通りです。
(住民税の所得割額 × 20%) ÷ (90% − 所得税率 × 1.021) + 2,000円
この計算式に使われる「住民税の所得割額」や「所得税率」は、源泉徴収票や住民税決定通知書を見ないとわかりません。
「自分で計算するのはやっぱり難しそう…」という方は、やはりシミュレーションツールの利用がおすすめです。
4. 確定申告不要!「ワンストップ特例制度」を賢く使おう
「確定申告が面倒だから…」とふるさと納税をためらっている方におすすめなのが、「ワンストップ特例制度」です。
これは、以下の2つの条件を満たせば、確定申告をしなくても税金の控除が受けられる制度です。
- 1年間の寄附先が5自治体以内
- 確定申告の必要がない給与所得者(会社員など)
制度を利用するには、寄附した自治体から送られてくる「申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類を添付して返送するだけです。
返送期限は翌年の1月10日(必着)なので、期限を過ぎないように注意しましょう。
まとめ)ふるさと納税は「始めるタイミング」が大切!
ふるさと納税は、実質2,000円の自己負担で、豪華な返礼品と税金控除の両方を得られるお得な制度です。
- まずは控除限度額を知ることから始めましょう。
- ワンストップ特例制度を使えば、確定申告なしで手続きが完了します。
- 迷ったら、まずは1つの自治体に寄附してみて、仕組みを体験してみるのがおすすめです。
ふるさと納税は、1年間の年収をもとに控除額が決まるため、早めに始めて、計画的に寄附することが大切です。
「自分の場合はどうなんだろう?」
「もっと詳しく知りたい!」
もし、ふるさと納税だけでなく、iDeCoやNISAなども含めた総合的な資産形成について相談したいことがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。専門家であるファイナンシャルアドバイザーが、あなたの状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。